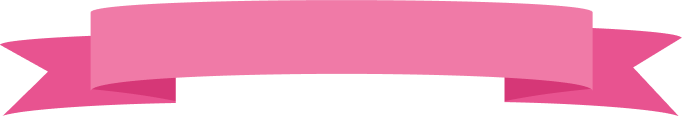債権譲渡
令和元(2019)年度税理士試験の国税徴収法第2問は、「(譲渡人)Aは(譲受人)Bとの間で)債権譲渡契約及び債権譲渡通知は有効なものとする。」、「(債務者)Cは、平成31年2月28日、Bから、「前記事項証明書」を添付した「債権譲渡通知書」を受け取っていた。」、「譲渡禁止特約は付されていない」と記述されています。本節では、債権譲渡(民法)について解説します。なお、消費税法6条1項に、「国内において行われた資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と規定されており、同表第2号に、有価証券等の譲渡が挙げられています。有価証券等には、貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権が含まれます(消基通6-2-1(二)ので、(金銭)債権譲渡は、消費税が非課税です。1 債権譲渡とは?債権譲渡とは、譲渡人と譲受人との間の契約によって、債権の同一性を保ったまま債権を移転させることをいいます。債権者が譲渡されるのは、支払期限前に現金化するためや代物弁済(3-8(2) p.206参照)のためなどです。◎債権譲渡旧債務者(譲渡人)→ 債務者 → 新債務者(譲受人)2 債権の譲渡性(1)譲渡の自由債権は、原則として自由に譲渡することができます(民法466条1項本文)。譲受人と譲渡人との合意で足り、譲渡契約の当事者ではない債務者の同意は必要ありません。(2)譲渡の制限債権の性質が譲渡を許さないときは、譲り渡すことができません(同条1項但書)。例えば、使用貸借権(民法594条2項、3-10(2) p.214参照)や賃借権(民法612条1項、1-7(7) p.55参照)は、債務者によって承諾が認められない限り、自由に譲り渡すことができません。また、法律で禁止されているときは、債権譲渡はできません。例えば、扶養請求権は、特定の債権者に対して給付されることが必要なため、譲渡が禁止されています(民法881条)。これに対して、債権者と債務者との間で特約を結び、債権譲渡を禁止・制限することができますが、原則として、それに反してなされた債権譲渡も有効です(民法466条2項)。例外として公的年金債権についての特約がある(民法466条の5)。そのうえで、一定の譲受人に対しては債務の履行を拒むことができるとすることで、債務者の保護が図られています(同条3項)。債権譲渡の禁止・制限の特約は、債務者の同意なき譲渡(例、預金債権)が主張して付されることが多いです。(3)将来債権の譲渡意思表示の時に現に発生していない債権(将来債権)を譲渡することもできます(民法466条の6第1項)。例えば、裁判所に診療報酬債権を譲渡することやBに銀行から金銭を借り受ける診療報酬債権を譲渡することができます。3 債権譲渡の対抗要件(1)債務者に対する対抗要件と第三者対抗要件債権譲渡は、譲渡人(譲受人ではない)が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません(民法467条1項)。債務者に対抗するためには、通知または承諾があればよいのですが、第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(同条2項)。確定日付のある証書とは、内容証明郵便や公正証書です。例えば、債権の二重譲渡があった場合に、第一譲受人と第二譲受人の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日時の先後によって決まります。譲渡契約の締結日時の先後ではありません。また、債務者が異議を述べずに承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由(例、弁済、相殺)があっても、これをもって譲受人に対抗することができません(民法468条1項)。譲受人の信頼を保護するためです。COLUMN 債権譲渡登記譲渡人が法人の場合、民法の対抗要件制度(本節の(1))による債権譲渡以外に、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」による債権譲渡を選択することもできます。この法律による債権譲渡は、債務者以外の第三者に対する対抗要件が分離されています。法律の定める債権譲出ファイルに記録されれば、債務者以外の第三者に対する対抗要件である、確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。債務者に対する第三者対抗要件を具備することです。これに該当するためには、さらに、譲渡人または譲受人が債務者に対して登記事項証明書を交付して通知することなどが必要です。本節の冒頭で紹介した試験問題では、債権譲渡登記がなされ、第三者対抗要件を具備するとともに、債務者が、譲渡人から登記事項証明書を添付した債権譲渡契約書を受け取っており、債務者対抗要件も具備しています。POINT 1債権譲渡とは、譲渡人と譲受人との間の契約によって、債権の同一性を保ったまま債権を移転させることをいう。債権者と債務者との間で特約を結び、債権譲渡を禁止・制限することはできるが、原則として、それに反してなされた債権譲渡も有効である。債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。確定日付のある証書によるものでなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。第三者対抗要件を備えた債権譲渡の優劣は、確定日付のある証書による債権譲渡通知が債務者に到達した日時の先後によって決まる。
詐害行為取消権
平成29(2017)年度税理士試験の国税徴収法第2問は、「納税者が滞納者を国の徴収を免れるため財産を処分したと認められる場合、国は詐害行為取消権の行使を請求し、その取消しを訴えたい」と出題されています。詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関する法律と並行して適用される規定であり、通則法第42条に定められています。本節では、詐害行為取消権(民法)について解説します。1 詐害行為取消権とは?詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができる債権者の権利です(民法424条1項本文)。債権者が債務者の財産管理への介入を認める例外的な権利です。債務者が責任財産(担保物権を持たない債権者への弁済に充てられる債務者の財産)を減少させる行為をしたときに、その行為を取り消すことによって、責任財産の保全を図ります。例えば、多額の負債を抱えた債務者が、唯一の財産である不動産を親族に贈与したときに、債権者は債務者の親族に対して贈与契約の取消しを請求します。2 詐害行為取消権を行使する相手方詐害行為取消権は、裁判上行使しなければなりません。債務者が詐害行為取消権を行使する場合の相手方は、受益者(債務者の詐害行為によって利益を受けた者)または転得者(受益者から財産を取得した者)です(民法424条の2第1項)。債務者は相手方となりません。詐害行為取消権に係る訴えを提起したときは、債務者は、債権者に対し、遅滞なく訴訟告知をしなければなりません(同条2項)。詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者(及びそのすべての債権者)に対しても効力を有するため(民法425条)、債務者の手続保障を図るためです。3 詐害行為取消権の要件受益者を相手方とする場合、詐害行為取消権を請求するための要件は、下記のとおりです。(1)債権者の要件まず、債権者に対する債権(被保全債権)が金銭債権であることです。また、債務者の責任財産の保全が制度趣旨であるため、全額債権であることが要件となります。次に、被保全債権が詐害行為の発生以前に生じたものであることが要件です(民法424条3項)。被保全債権の発生が見込まれた時点での債務者の責任財産をあてにして期待することが保護に値するからです。取戻権は詐害行為の発生の前後を問いません。(2)債務者の要件債務者が詐害行為を目的とする行為をしたことが要件です(同条2項)。債務者による家族法上の行為を取り消すことができるかどうかは問題となります(本節のCOLUMN)。次に、債務者が行為によって債務超過を来すこと(または債務超過を強めること)が要件です。詐害行為は債権者を害することにならなければなりません。債務者が無資力でなければなりません。詐害行為だけでなく、債務者の資力は回復し、債務者は、債務の履行が可能になります。(3)受益者の抗弁受益者は、①詐害行為時において債務者を害することを知らなかった(同条1項但書)、②被保全債権が強制執行により実現することのできないものではない(同条4項)、③被保全債権において担保が設定された債権(担保によって優先弁済権が及ぶ範囲)でない(同条4項)という反論をすることができます。4 詐害行為性(1)財産を減少させる行為財産を減少させる行為(例、無償行為、低額譲渡)は、詐害行為性が認められます。(2)相当の対価を得てした財産の処分行為債務者が自己の所有不動産を売却し、受益者から相当の対価を取得しているときは、原則として、詐害行為にはなりません。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、詐害行為となります(民法424条の2)。① 行為が、不動産の金銭への換価その他の処分による財産の種類の変更により、債権者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をするおそれを生じさせるものであること② 債務者が、行為の当時、対価として取得した金銭などについて、隠匿等の処分をする意思を有していたこと③ 受益者が、行為当時、①②を知っていたこと(3)既存の債務の担保の供与または債務の消滅に関する行為債務者がした既存の債権についての担保提供または債務消滅に関する行為(例、弁済)は、原則として、詐害行為にはなりません。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、詐害行為となります(民法424条の3)。① 行為が、債務者が支払不能の時に行われたものであること② 行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであることまた、上記に掲げる要件のいずれにも該当する場合に、受益者が、債務の履行またはその時期が債務者の義務に属せず、またはその方法が債務者の義務に属しないものであるときは、上記の行為(及び上記に加えて、受益者が支払不能であったことを知っていたこと)を詐害行為となります。5 詐害行為取消権の効果(1)詐害行為の取消しと逸出財産の取戻し詐害行為取消権の効果は、詐害行為の取消しと逸出財産の取戻しです。残余財産の返還が困難である場合、現実の返還が困難であるときは、債務者は、その価額の償還を請求することができます(民法424条の6)。(2)逸出財産の返還の方法詐害行為取消権は、債権者の責任財産の保全を目的とするため、逸出財産は債務者に返還されるのが原則です。逸出財産が不動産の場合(例、受益者への移転登記)は、移転登記が抹消され、債務者に返還されます。一方、金銭または動産の場合、取消権者は、受益者・受領権限が認められており、受益者に対して、自己に返還することを求めることができます(民法424条の9)。返還を受けた取消権者は、受益者に対する債務と相殺することにより、債権を回収することができます。(3)受益者の権利受益者は、債務者がした財産の処分行為(詐害行為)が取り消されたときは、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができます。債務者が反対給付の返還をすることが困難であるときは、価額の償還を請求することができます(民法424条の2)。また、債務者がした債務の消滅行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還したときは、受益者の債務者に対する債権は回復します(民法425条の3)。6 詐害行為取消権の抗告訴訟期間詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、または債務者の行為の時から10年を経過したときは、提起することができません(民法426条)。詐害行為取消権は、債権者の知らない行為を対象とするものであり、第三者に与える影響も重大な処分を伴うものであり、第三者に与える影響が少ないため、法律関係を速やかに確定する必要があるから出訴期間が短くなっています。7 詐害行為取消権の課税関係取り消される行為は財産を処分する行為であり、受益者に移転した財産は課税されます(民法424条の8第2項)。詐害行為取消権により取り消されるまでには、受益者は、受益者としての地位を享受できます。COLUMN 家事事件法上の詐害行為取消権債権者がした家事事件法上の詐害行為取消権を債権者がした家事事件により生ずる債権は、特別の事情がある場合を除き、無効とされます(1-1(2) p.424参照)。遺産分割の前提となるのは、遺産分割が前提となり、相続人が債務者である場合の債務超過の相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりますが、遺産分割(1-15(1) p.243参照)は、取り消すことはできません。相続財産が確定するまでの間に、相続人がした相続財産の処分は、遺産分割の結果とは異なる場合があります。これに対して、遺産分割は、財産を目的とする行為といえるため、詐害行為取消権の対象となります。POINT 1詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる債権者の権利である。詐害行為取消権は、裁判上行使しなければならない。詐害行為取消権の効果は、取消しと逸出財産の取戻しである。逸出財産の価額償還が原則だが、債権者は、その価額の償還を請求することができる。詐害行為取消権の責任財産の保全を目的とするため、逸出財産は、債務者に返還されるのが原則である。また、金銭の場合には、取消権者は、自己に返還を求めることができる。
留置権
平成29(2017)年度税理士試験の国税徴収法第2問は、「留置権」に関する問題が問われています。1項、P株式会社は、所有する自家用車が故障したため、平成28年9月1日、X株式会社に修理を依頼した。P株式会社が修理中の提携会社のA自動車をX税務署長が差し押さえ、その後、修理は完了したものの、所有者Aが修理代金(100万円)を支払わないため、P株式会社が引き続き自動車(評価額800万円)を占有している」と記述されています。本節では、留置権(民法)について解説します。1 留置権とは?留置権とは、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときに、債権の弁済を受けるまで、その物を留め置くことができる権利です(民法295条1項本文)。債務の弁済を間接的に強制するものです。本節の冒頭で紹介した試験問題では、X自動車にP株式会社が修理代金債権に関して生じた修理代金債権の弁済を受けるまで、自動車を留置することができます。留置権は、法律の定める一定の要件を充たせば当然に発生する法定担保物権です。抵当権(1-3(2) p.30参照)や質権(1-4(2) p.42参照)のような、当事者の合意により成立する約定担保物権とは異なります。2 留置権の成立要件(1)他人の物の占有留置権が成立するには、他人の物を占有していることが要件となります。目的物は、債務者が所有する物に限定されません。また、占有は成立要件であるだけでなく存続要件でもあり、留置物が占有を失うと、留置権は原則として消滅します(民法302条本文)。留置権が成立するには、目的物に対して生じた債権を有すること、すなわち被担保債権と目的物との牽連性が認められることが要件となります。本節の冒頭で紹介した試験問題では、修理代金債権と自動車との間に(2-11(3) p.153参照)牽連性が認められます。物の欠陥を原因として占有者が損害を被った場合の損害賠償請求権と物との間には、牽連性が認められます。(2)被担保債権の履行期留置権が成立するには、被担保債権の履行期が到来していることが要件となります(民法295条1項)。3 留置権の効力(1)留置的効力留置権の効果として、留置物を占有し続けることができます。被担保債権の弁済と留置物の引渡しは引換えとなります。(2)対抗的効力留置権は(債権ではなく)物権なので、(債務者に限らず)すべての人に対して主張することができます。本節の冒頭で紹介した試験問題では、P株式会社は、X税務署長(国)に対しても、X会社の自動車に対する留置権を主張することができます(本節のCOLUMN1)。(3)留置物の使用権留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用することはできません(民法298条2項本文)。本節の冒頭で紹介した試験問題では、P株式会社は、債務者の承諾がなければ自動車を使用することはできません。(4)優先弁済的効力留置権には、優先弁済的効力はありません。原則として、目的物の競売から優先弁済を受ける権利はありません(本節のCOLUMN1)。しかしながら、留置権者は、下記のとおり、事実上の優先弁済の地位が認められています。自分だけが履行して相手方から反対給付を受けることができないという事態の発生を防ぐことで、当事者間の公平を確保するものです。また、相手方の履行を促すという効果もあります。双務契約での引渡しが必要となる場合には、留置権と同時履行の抗弁権のいずれも行使することができます。POINT 1留置権とは、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときに、債権の弁済を受けるまで、その物を留め置くことができる権利である。留置権は、法律の定める一定の要件を充たせば当然に発生する法定担保物権である。留置権には、目的物の換価代金から優先弁済を受ける権利はない(滞納処分による換価の場合を除く)が、留置権者には、事実上の優先的地位が認められている。COLUMN 2 商事留置権本節で解説した民法上の規定に定められた留置権です。この他、商法に定められた商事留置権(商法521条)などがあります。商事留置権は、継続的な取引が行われる商人Aと商人Bとの間で生じた債権であれば、債権全体を担保する目的で、商人Bの所有物を留置することができるとされています。商事留置権の成立要件には、①被担保債権が、商人A間において両方にとって商行為となる行為から生じたものであること、かつ②非牽連していること、③目的物が、債務者との間における商行為によって占有した債務者の所有する物であることなどです。民法の留置権との相違点は、被担保債権と目的物との牽連性は不要ですが、上記のとおり特定されていること、目的物が債務者の所有物に限定されることなどです。COLUMN 3 同時履行の抗弁権本節の冒頭で紹介した留置権は、当事者の意思によらず法律の規定によって成立する担保物権です。双務契約(当事者の双方が対価的な意味のある債務を負担する契約)であるため、P株式会社はX会社に対して同時履行の抗弁権(民法533条)を主張することができます。同時履行の抗弁権の効果は、双務契約の一方の当事者は、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるというものです。主観的事情ではなく客観的事情が認められる限り、留置権とは異なり、対価的な効力はありません。
遺留分
遺言書を作成するにあたって知っておくべき事項として遺留分があります。遺産分割のすべてを相続人の1人に相続させるという内容の遺言書を作成すると、他の相続人の遺留分を侵害し、相続開始の死後に争いが生じるおそれがあります。そこで、各相続人の遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することも多いです。本節では、遺留分(民法)について解説します。1 遺留分とは?被相続人の財産の中で一定の相続人に留保(最低限保障)されている持分的利益を「遺留分」といいます。皆の言い分とすると、遺留分とは、一定の相続人に対して認められる、遺言などによっても奪われることのない、遺産の中の一定割合の持分利益のことです。被相続人からすると、贈与や遺贈(3-22 p.271参照)などによって自分の財産を自由に処分することに対して制限を加えられることになります。遺留分権利者となるのは、相続人(兄弟姉妹を除く)です(民法1042条1項)。そして、各遺留分権利者に留保された持分的割合(個別的遺留分)は、直系尊属のみが相続人である場合は1/3×法定相続分、それ以外の場合は1/2×法定相続分です。2 遺留分侵害額(1)遺留分額遺留分額は、遺留分を算定するための財産の価額に個別的遺留分を乗じて算定します。遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時において有した財産(遺贈財産を含む)の価額に、被相続人が相続人に対して行った贈与の価額を加え、相続債務の全額を控除した額です(民法1043条1項)。加算対象となる被相続人の贈与は限定されています(民法1044条)。①相続開始前の1年間にされた贈与、②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与、③相続開始前の10年間になされた、相続人に対する、婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本としてなされた、相続人に対する、感謝もしくは扶養を継続するための利益またはこれに準ずる利益(特別受益、3-20(2)p.262参照)などです。①と③は、相続人に対する贈与に限定されません。①の1年間の限定は、遺留分侵害額を負担する立場になる受遺者の保護のためです。②は、受贈者を保護する必要がないため、贈与時期による限定はありません。③は、実質的に相続財産の前渡しといえるので10年間の贈与が対象となります。(2)遺留分侵害額遺留分侵害額は、遺留分額から、「遺留分権利者が受けた遺贈及び特別受益である贈与の価額」及び「具体的相続分(寄与分は考慮しない)に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額」を控除し、「遺留分権利者が承継する相続債務の額」を加算して算定します(民法1046条2項)。控除される「遺留分権利者が受けた特別受益である贈与」には、内容が特別受益に該当するものに限定されますが、贈与時期による限定はありません。上記(1)の③の贈与との違いには注意が必要です。◎遺留分侵害額① 遺留分を算定するための財産の価額相続開始時の相続財産(遺贈財産を含む)の価額 + 被相続人が贈与した財産の価額(限定あり)- 相続債務の全額② 具体的相続分上記① × 具体的相続分率③ 具体的利益額具体的相続分 + 「遺留分権利者が受けた遺贈及び特別受益である贈与の価額」-「遺留分権利者が承継する相続債務の額」3 遺留分侵害額の請求遺留分権利者やその承継人などが行為の利益を放棄できません。侵害された遺留分権利者は、受遺者(特定財産承継遺言(3-22(2)p.274参照)により財産を承継し、または相続分の指定を受けた相続人を含む)または受贈者に対して、金銭債権を取得し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項、遺留分侵害額請求権)。なお、令和元(2019)年7月1日以降に開始した相続については、金銭債権の取得ではなく、遺留分減殺請求権として、個々の相続財産について(例)共有持分権が発生することになっていました(3-9 COLUMN p.209参照)。遺留分権利者が価額弁償を選択しない場合に、共有関係を解消するには共有物分割を行う必要がありました。改正により国民から「減殺」という文言は削除されました。4 遺留分侵害額の負担額受遺者または受贈者は、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継または相続分の指定による財産の取得を含む)または贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る)の目的の価額を限度として、次のとおり、遺留分侵害額を負担します(民法1047条1項)。① 受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担する。② 受遺者が複数あるとき、または受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者または受贈者は、その目的の価額の割合に応じて負担する。③ 受贈者が複数あるとき(同時にされた贈与の場合を除く)は、後の贈与に係る受贈者から順次に前の贈与に係る受贈者が負担する。ただし、受遺者または受贈者が、遺留分侵害額について(法定相続分ではない)を控除した額が上限となります。5 遺留分侵害額請求権の時効期間制限遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも消滅します(民法1048条、除斥期間)。6 遺留分の放棄相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます(民法1049条1項)。被相続人によって放棄を強要され、濫用されるおそれがあるため、家庭裁判所による許可を必要とします。一方、相続開始後においては、遺留分の放棄や遺留分侵害額請求権の放棄は、自由にすることができます。家庭裁判所の許可は不要です。遺留分を放棄しても、相続人としての地位は失いませんし、他の相続人の遺留分に影響を及ぼしません(同条2項)。7 遺留分の課税関係遺留分侵害者は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金額が確定したことにより、申告書を提出した相続税または既に決定を受けた相続税について金額が過大となったときは、確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、更正の請求をすることができます(相続税法32条1項3号)。一方、遺留分権利者は、遺留分侵害額の請求に基づき支払いを受ける金員の額が確定したため、相続税申告書の提出期限後に、新たに申告書を提出すべき要件に該当することとなったときは、期限後申告書を提出することができます(相税法27条1項)。また、相続税申告書の提出後に、既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができます(相税法31条1項)。遺留分権利者の上記申告書は、義務ではありません。なぜなら、遺留分侵害額の請求に基づき支払いを受ける金員の額が確定しても、相続財産額の変動はないからです。もっとも、遺留分権利者が更正の請求をしたときは、税務署長が税額の更正の決定または決定をするため、遺留分権利者に相続税の納付義務が生じます。なお、遺留分侵害額請求について代物弁済の合意をした場合の課税関係については、3-8 COLUMN(p.207参照)で解説しています。POINT 1被相続人の財産の中で一定の相続人に留保(最低限保障)されている持分的利益を「遺留分」という。侵害された遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分侵害額の請求を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも消滅する。